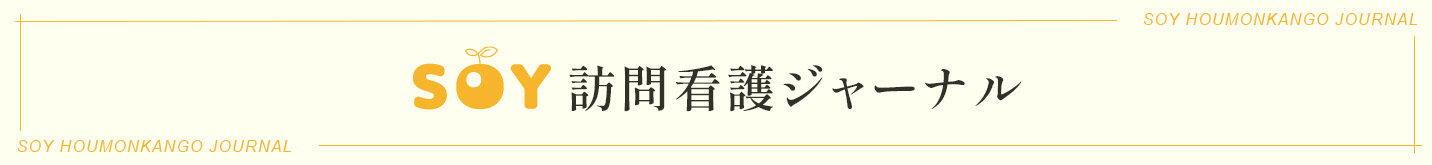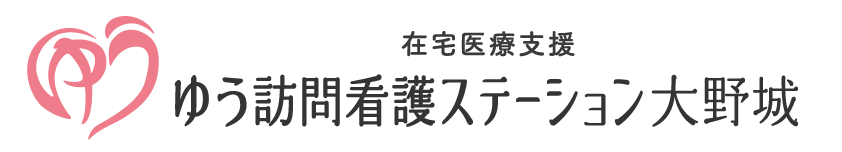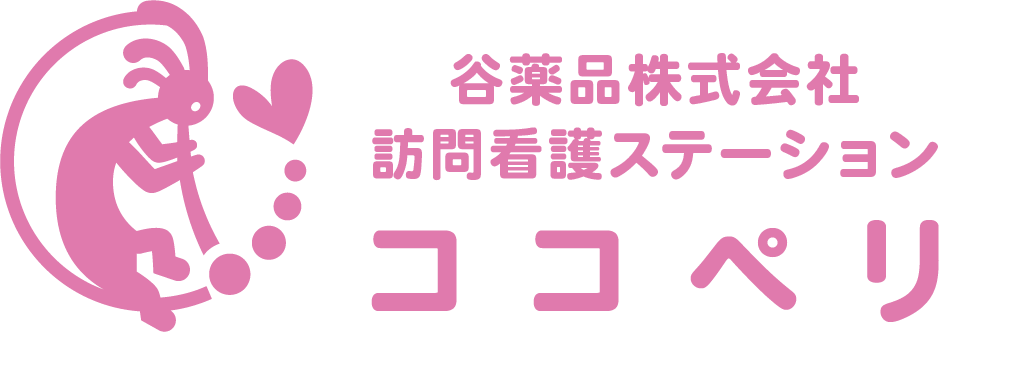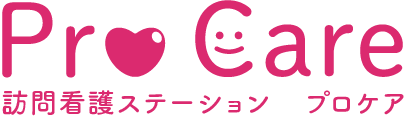こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人SOYの大山あみです。
高齢のご家族が入院し、これから退院を迎える方の中には「退院後、一人暮らしを続けられるのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
高齢者が入院すると、身体機能の低下や生活リズムの変化などにより、退院後の一人暮らしに不安を抱えることがあります。
今回のコラムでは、高齢者が退院後に一人暮らしを継続するために必要な準備や利用できるサービス、施設入居の判断基準などについて解説します。
ご本人の希望を尊重しながらも、安全に生活を送るための選択肢を一緒に考えていきましょう。
目次
一人暮らしの高齢者が抱える退院後の課題とは
高齢者が退院後に一人暮らしを始める際には、さまざまな課題や不安が生じることがあります。
一人暮らしの高齢者の退院後の課題
まずは、どのような課題があるのかを理解しましょう。
身体機能の低下による生活上の困難
入院により、筋力低下や日常生活動作の低下が進み、これまでできていた家事や身の回りのことが困難になる場合があります。
特に歩行障害があると、自宅内での移動や買い物などの外出に苦労し、転倒リスクも高まります。
退院後しばらくは疲労感やしびれなどの症状が残り、入浴や調理といった日常生活に影響をおよぼすこともあるでしょう。
服薬管理や医療ケアの問題
退院後も継続的な薬の服用や特定の医療ケアが必要な場合、自己管理が難しくなることがあります。
薬の飲み忘れや間違った服用方法は病状の悪化を招く恐れも。
また、インスリン注射や痰の吸引など専門的な医療ケアが必要な場合、一人では対応が難しいケースも少なくありません。
食事や栄養管理の課題
退院後は適切な栄養摂取が回復に重要ですが、買い物や調理が難しくなると、栄養バランスの偏った食生活になりがちです。
特に体力が低下している時期は、十分な食事を準備するエネルギーがなく、食欲不振も相まって栄養状態が悪化することがあります。
緊急時の対応の不安
一人暮らしの場合、急な体調変化や転倒などの緊急事態が起きた時に助けを呼べるか不安が大きいものです。
特に夜間の緊急時には、対応が遅れることによって重大な事態につながる恐れもあります。
精神的な孤独感
退院して自宅に戻っても、体調の不安や将来への不安から、精神的に不安定になることがあります。
人との交流が減少することで孤独感が強まり、意欲の低下やうつ状態に陥るケースもあります。
高齢者の退院後の一人暮らしにはメリットもある
自宅で生活することには、課題もある一方で、多くのメリットがあります。
まず、住み慣れた環境で自分のペースで生活できる「自由度の高さ」は大きな魅力です。
長年住み慣れた家での生活は心理的な安定をもたらし、それが心身の健康につながることも少なくありません。
また、近隣との交流関係が維持でき、自分の持ち物に囲まれた生活は自己尊厳を保つことにもつながります。
さらに、自分でできることは自分で行うことで、残存機能の維持・向上が期待できます。
ペットを飼っている高齢者の場合、ペットと一緒に生活を続けられることも大きな喜びとなるでしょう。
高齢者が退院後に一人暮らしをするには?
高齢者が退院後も一人暮らしを継続するには、本人の自立心を尊重しながらも、適切なサポート体制を整えることが大切です。
退院前に準備すべきこと
退院後の一人暮らしを成功させるためには、退院前からの準備が重要です。
医療ソーシャルワーカーや看護師への相談
入院中から、退院後の生活について医療ソーシャルワーカーや病棟看護師に相談しましょう。
退院前カンファレンスでは、退院後の生活で心配なことや必要なサポートについて話し合います。
要介護認定の申請についても、必要に応じて進めておきましょう。
住環境の整備
自宅のバリアフリー化や手すりの設置、ベッドの配置変更など、安全に過ごせるよう住環境を整備する必要があります。
介護保険を利用して住宅改修をすることも検討しましょう。
必要な福祉用具の準備
歩行器や杖、ポータブルトイレなど、日常生活をサポートする福祉用具を準備します。
これらは介護保険の福祉用具貸与サービスを利用することができます。
在宅サービスを活用する
退院後に安心して一人暮らしをするためにも、さまざまな在宅サービスを組み合わせて活用するのがおすすめです。
代表的なものをご紹介します。
訪問看護
看護師が定期的に自宅を訪問し、健康状態の確認や医療処置、服薬管理などを行うサービスです。
病状の観察や胃ろう管理など専門的なケアも受けられるため、医療ニーズの高い方も在宅生活を続けられます。
訪問看護の利用方法については、こちらのコラムで詳しくご紹介しています。
ぜひあわせてご覧ください。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、日常生活の動作訓練や機能回復訓練を実施します。
自宅環境での具体的な動作練習は、実際の生活に即した機能回復につながるメリットがあります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事の準備や掃除、洗濯などの生活援助から、入浴や排泄の介助などの身体介護まで提供します。
家事や身の回りのことに困難を感じる方にとって、日常生活を支える重要なサービスです。
通所介護(デイサービス)
日中、デイサービスセンターに通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサポートを受けるサービスです。
ほかの利用者様との交流は社会性の維持につながり、孤独感の解消にも役立ちます。
緊急通報システム
ボタン一つで緊急連絡ができる通報システムで、急な体調変化や転倒時の対応に備えることができます。
自治体によって提供内容は異なりますが、高齢者の一人暮らしを支える安心設備として重要です。
高齢者の退院後、施設に入居する際の判断基準は?

一人暮らしの継続が難しいと判断される場合には、施設入居を検討することも選択肢の一つです。
どのような場合に施設入居を検討すべきか、判断基準を解説します。
健康状態からの判断
医療ケアの必要性が高いか、認知症の症状があるか、または要介護状態の程度により判断します。
胃ろうや酸素吸入、たん吸引など日常的かつ頻繁なケアが必要な場合、在宅での対応が難しくなるケースがあります。
認知症が進み、食事や服薬を忘れてしまうことが増えたり、火の取り扱いや戸締りなど生活の安全に関わる判断が難しくなったりした場合も、見守り体制のある環境が望ましいでしょう。
また、日常生活全般にわたって介護を要する状態になると、在宅での一人暮らしを続けるのは難しいかもしれません。
住環境からの判断
住宅のバリアフリー化が困難な場合や、集合住宅での生活が困難な場合に施設入居を考えることがあります。
階段が多い住宅や段差の多い、廊下や出入口が車イスのサイズに合わないなどの環境で改修が難しい状況では、施設入居を考える必要があるでしょう。
家族状況からの判断
近隣に支援できる家族がいない場合や、家族の負担が過大になる場合は施設入居を検討することがあります。
緊急時にすぐに駆けつけられる家族がいない場合、安全面からも施設入居がおすすめです。
本人の意思の尊重
施設入居を検討する際には、本人の意思を最大限尊重することが大切です。
ただし、本人が強く在宅を希望していても、安全面で大きな懸念がある場合は、専門家を交えた話し合いが必要です。
医師や医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャーなど第三者から説明を受けることで、本人が納得して入居を決断できることもあります。
退院後の一人暮らしが難しい場合の選択肢
一人暮らしの継続が難しい場合は、以下のような施設の利用も検討しましょう。
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
身体状況や認知機能の状態、本人の希望、家族の状況に合わせて検討することになります。
安全に生活できることや家族の負担なども考慮しつつ、こちらもできる限り本人の意思を尊重した選択が理想的です。
利用条件や費用、サービス内容は施設によって異なりますので、複数の施設を比較検討することをおすすめします。
高齢者が退院後の一人暮らしを継続するには適切なサポートと準備が鍵
高齢者が退院後に一人暮らしを継続するためには、身体機能の低下による生活上の困難、服薬管理や医療ケア、食事の準備、緊急時対応など、さまざまな課題があります。
しかし、住み慣れた環境で自分のペースで過ごせることは高齢者のQOLの維持に大きな意味があり、本人の希望を尊重しながら安全に暮らせる環境を整えることが大切です。
訪問看護や訪問介護、デイサービスなどの在宅サービスの利用や、緊急通報システムの活用、定期的な見守りなどを組み合わせながら、安全に一人暮らしができる体制を検討しましょう。
一方で、一人暮らしが難しい場合には、グループホームや介護施設など、自宅以外の選択肢を検討することも必要です。
高齢者の退院後一人暮らしには、本人の意思と自立を尊重しつつも、安全面にも配慮した総合的な判断が求められます。
退院前から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーに相談し、適した生活環境を一緒に考えていきましょう。