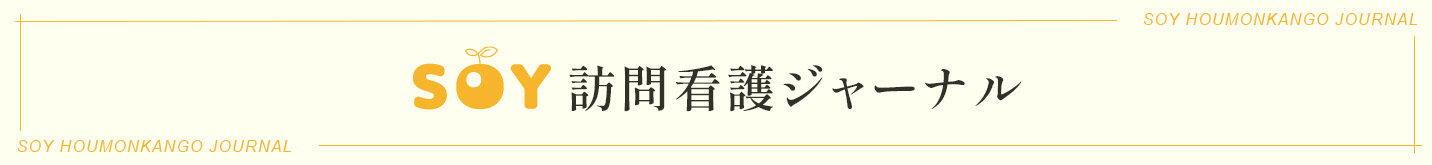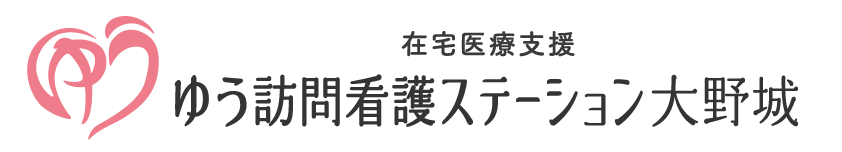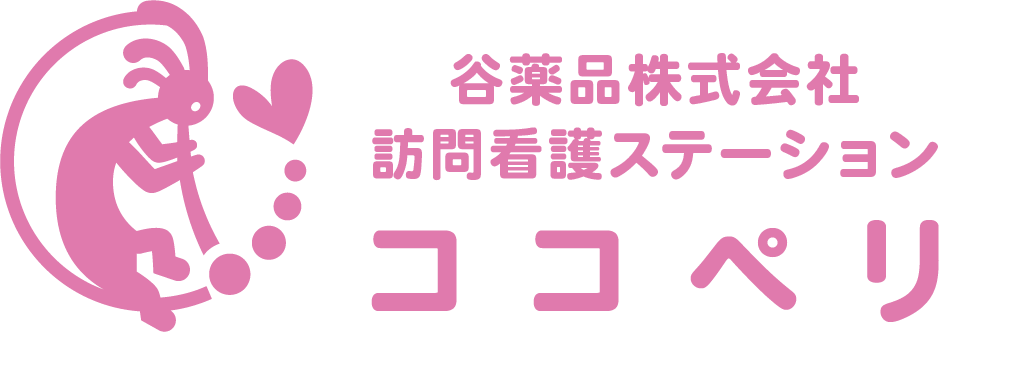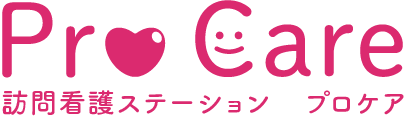こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの安立あみです。
要支援認定を受けた方やそのご家族にとって、在宅での療養生活を安心して送るためのサービス選択は重要な課題です。
その中でも「介護予防訪問看護」は、要介護状態への進行を防ぎ、自立した生活を維持するための重要なサービスとして注目されています。
通常の訪問看護との違いや具体的なサービス内容について、正しく理解することで、ご自身やご家族の状況に最適なケアを選択できるでしょう。
目次
介護予防訪問看護とは?
介護予防訪問看護は、要支援1または要支援2の認定を受けた方に向けて提供される在宅医療サービスです。
訪問看護ステーションや医療機関から看護師などの専門職が利用者様のご自宅を訪問し、医師の指示に基づいて介護予防に必要な療養支援や日常生活の援助を行います。
目的と対象者
介護予防訪問看護は、要介護状態になることを予防し、現在の身体機能や生活機能を可能な限り維持・向上させることを主な目的としています。
利用者様が住み慣れた環境で自立した日常生活を継続できるよう、専門的な観点からサポートを提供します。
サービスの対象となるのは、お伝えしたように「要支援1・2」の認定を受けた方です。
これらの方は日常生活の基本的な動作はおおむね自立しているものの、将来的な介護状態への進行を防ぐための支援が必要とされます。
通常の訪問看護との違い
介護予防訪問看護と要介護者向けの訪問看護では、サービスの目的と提供内容に明確な違いがあります。
介護予防訪問看護では、現在の生活機能の維持・向上と状態悪化の防止に重点を置いたケアを提供します。
一方、要介護者向けの訪問看護では、既に介護が必要な状態の方に対して、より包括的な医療ケアや日常生活の介助を中心とした支援を行います。
さらに、介護保険の報酬体系も異なります。
介護予防訪問看護のほうが基本報酬の単位数は低く設定されており、加算項目についても、介護予防訪問看護では一部の加算が設定されていないなどの違いがあります。
要介護認定については、「要介護認定を受けるには?申請方法や認定までの流れを解説」をご覧ください。
介護予防訪問看護で受けられるサービス

介護予防訪問看護では、利用者様の心身の状態に応じて、以下のようなサービスを組み合わせて提供します。
健康状態の観察と管理
血圧や体温などのバイタルサインチェックを通じて、利用者様の健康状態を定期的に把握します。
体調の変化を早期に発見し、適切な対応につなげることで、病状の悪化や体調不良を予防します。
身体機能の維持・向上支援
日常生活動作の訓練やリハビリテーションを実施し、現在の身体機能を維持・向上させます。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による専門的なリハビリテーションも提供可能です。
日常生活のケア
清拭や洗髪などの清潔保持、食事に関する支援、排泄のケアなど、日常生活に必要な支援を行います。
また、栄養管理や水分管理についても専門的な視点からアドバイスを提供します。
医療的な処置とケア
医師の指示に基づいて、褥瘡の予防・処置、医療機器の管理、必要な医療処置を実施します。
人工呼吸器やカテーテルなどの医療機器についても、適切な管理とケアを提供します。
認知症ケアと家族支援
認知症の症状がある利用者様には、症状に応じた専門的なケアを提供します。
また、療養生活に関する相談や、ご家族への介護方法の指導も重要なサービスの一つです。
緊急時対応
24時間365日の対応体制により、夜間や早朝、緊急時にも必要なケアを受けることができます。
ただし、これらの時間帯では利用料が割増となります。
訪問看護の内容や利用条件は「訪問看護でできること・できないこととは?利用条件も確認」で詳しく解説しています。
介護予防訪問看護の利用料はどのくらい?
介護予防訪問看護の利用料は、訪問する事業所の種類と訪問時間によって設定されています。
【訪問看護ステーションからの訪問の場合】
- 20分未満:303単位/回
- 30分未満:451単位/回
- 30分以上1時間未満:794単位/回
- 1時間以上1時間30分未満:1,090単位/回
【病院・診療所からの訪問の場合】
- 20分未満:256単位/回
- 30分未満:382単位/回
- 30分以上1時間未満:553単位/回
- 1時間以上1時間30分未満:814単位/回
【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問】
- 1回20分:284単位/回(週6回を限度)
※2025年7月時点の情報です。
上記の単位数に、事業所が所在する市区町村ごとの地域加算という上乗せ率をかけ合わせた金額が介護報酬額となります。
利用者様は、自身の所得に応じた自己負担割合に応じて、1割から3割のいずれかの自己負担を支払います。
単位は、1点10円で計算します。
例えば、自己負担1割の利用者様が、地域加算の上乗せがない地域で、訪問看護ステーションの介護予防訪問看護のサービスを1時間利用した場合は1,090単位で、1,090円/回の自己負担が発生します。
各種加算について
基本料金に加えて、利用者様の状態や提供するサービス内容に応じて各種加算が適用される場合があります。
代表的な例としては、初回加算として、介護予防訪問看護を初めて利用する場合に300単位(3割負担の場合は900円、1割負担の場合は300円)が加算されます。
この加算は、過去2カ月間にその事業所からの訪問看護サービスを受けていない場合に発生します。
また、胃チューブや腹膜透析など特別な管理を必要とする利用者様に対しては、特別管理加算として1カ月ごとに250単位または500単位(3割負担の場合は750円または1,500円、1割負担の場合は250円または500円)の加算も。
そのほかにも、以下のような加算があります。
- 専門管理加算(250単位/月)
- 緊急時訪問看護加算(325~600単位/月)
- 口腔連携強化加算(50単位/回 ※月1回に限る) など
利用回数の制限について
介護予防訪問看護では、看護師による訪問に回数制限は設けられていません。
ただし、介護保険制度では支給限度額が設定されているため、限度額を超過した分については利用者様の全額自己負担となります。
一方で、理学療法士等のリハビリ職員による訪問については一定の制限があり、1日2回を超える訪問や、訪問時間の合計が40分を超えた場合は減算が適用されます。
また、訪問看護には「2時間ルール」が適用され、同日に複数回訪問する場合は原則として2時間以上の間隔を空ける必要があります。
2時間未満の間隔で訪問する場合は、それぞれの所要時間を合算して算定されます。
介護予防訪問看護とは自立支援を目的とした専門的ケア
介護予防訪問看護とは、要支援認定を受けた方の自立した生活を支援し、要介護状態への進行を予防することを目的とした専門的な在宅ケアサービスです。
健康状態の観察から医療処置、リハビリテーション、日常生活支援まで、幅広い内容のケアを通じて利用者様の生活の質向上をサポートします。
通常の訪問看護とは目的や対象者が異なり、予防的な観点からのケアに特化している点が特徴です。
国が定めた報酬単価に基づき、訪問時間や加算の有無によって算定され、介護保険の適用により1~3割の自己負担で利用できます。
訪問回数の制限はありませんが、基本的には介護保険の支給限度額内での利用となります。
医療と介護が連携したサポートで、住み慣れた環境で安心して暮らすとともに、将来の介護状態への進行を予防できます。