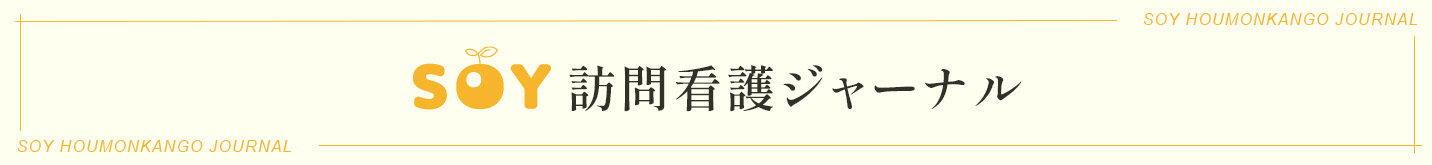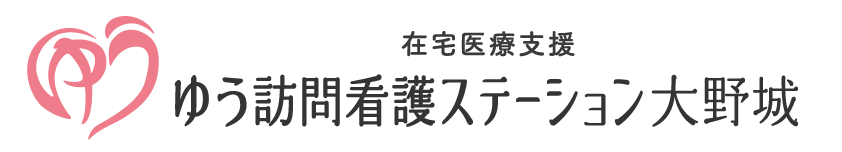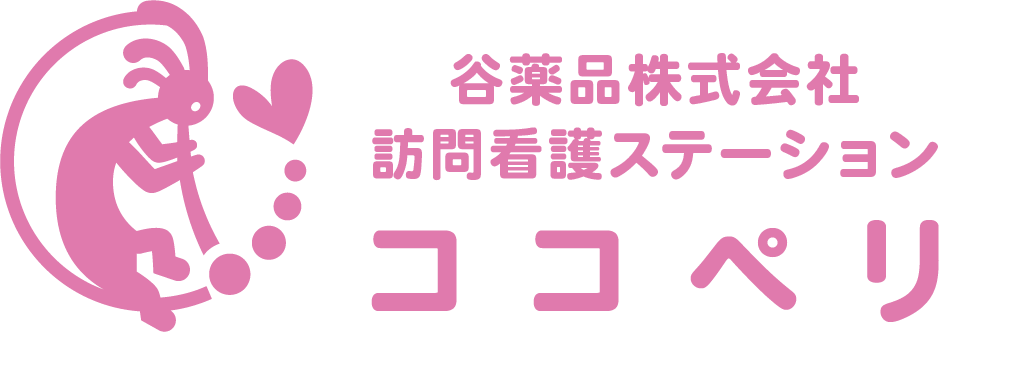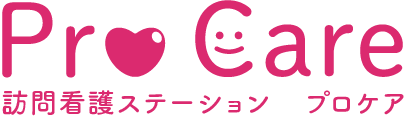こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの安立あみです。
訪問看護ステーションの開設をお考えの方は、開設に必要な基準や手順について不安や疑問をお持ちではないでしょうか。
訪問看護ステーションの開設には、法律で定められた基準を満たし、都道府県などへ申請をして指定を受ける必要があります。
今回のコラムでは、訪問看護ステーションの開設時に知っておくべき開設基準について詳しく解説します。
また、開設までの具体的な手順や必要な準備についてもお伝えしていきますので、開設までの道のりを一緒に見ていきましょう。
目次
訪問看護ステーションの開設基準
訪問看護ステーションを開設するためには、都道府県知事などの指定を受ける必要があります。
そして、この指定を受けるためには、「人員基準」「設備基準」「運営基準」という3つの重要な開設基準を満たすことが求められます。
それぞれの基準について、詳しく見ていきましょう。
人員基準
訪問看護ステーションの要となるのが、適切な人員配置です。
以下の基準を満たす必要があります。
- 看護職員(保健師、看護師、准看護師)が常勤換算で2.5人以上
- 上記のうち1名は常勤職員
- 管理者は保健師または看護師で、専従かつ常勤
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は必要に応じて配置
常勤換算とは、その訪問看護ステーションにおける4週間の勤務延べ時間数を、常勤者の勤務すべき時間数で割った数値を指します。
例えば、常勤職員の勤務時間が週40時間の場合、週20時間勤務のAさん、週30時間勤務のBさんは、常勤換算すると以下の計算の通り2人で1.25人 という換算になります。
(Aさん20時間+Bさん30時間)÷40時間=1.25人
設備基準
事業を適切に運営するために、専用の事務室と必要な区画や設備、備品などを備えることとなっています。
特に以下の5点について注意が必要です。
①事務室
明確な広さの規定はありませんが、デスクやキャビネットを置くことができ、業務を円滑に行うための広さが必要です。
また、独立性が必要で、個室がない場合はパーテーションやカーテンなどで区切り、専用の区画にします。
②相談室
プライバシーに配慮した独立性のある区画とします。
個室でなければパーテーションで仕切るなどの工夫が必要です。
③衛生設備、独立洗面台
感染症予防のために、衛生設備として独立洗面台を設置します。
石けん類、アルコール消毒、ペーパータオルなどを備え付けましょう。
④鍵付き書庫
個人情報を適切に管理するための鍵付きの書庫が必要です。
⑤防火対策
消火器の設置やスプリンクラーの位置なども確認が必要です。
運営基準
厚生労働省が定める運営基準に従って運営する必要があります。
具体的な運営基準については、厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に明記されています。
主な運営基準には以下のような項目がありますよ。
<サービス提供に関する基準>
- サービス内容の説明と同意取得
- サービス提供拒否の禁止
- 利用者様の状況把握と適切な対応
- ほかのサービス提供者との連携体制の構築 など
<業務管理に関する基準>
- 訪問看護計画書と報告書の作成
- 緊急時対応体制の整備
- 適切な勤務体制の確保
- 個人情報保護とプライバシーの遵守 など
訪問看護ステーションを開設する手順

開設までの具体的な手順について、流れに沿ってご紹介します。
目的と方針の策定
まずは、訪問看護ステーションを開設する意義と理念を明確にすることから始めます。
地域における医療・介護ニーズを丁寧に分析し、どのような対象者にどのようなサービスを提供していくのかを具体的に検討・決定し、明文化しましょう。
開設後の利用者様数の見込みや、必要となる訪問看護サービスの内容、重点的に取り組むべき領域などを明確にします。
法人設立
訪問看護ステーションは個人での開設ができないため、法人格の取得が必要です。
法人の形態には、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、株式会社、合同会社などがあり、それぞれ設立要件や必要資金が異なります。
また、定款の事業目的には、必ず「介護保険法に基づく訪問看護事業」を含めましょう。
行政との事前協議
開設予定地の市町村の介護保険担当課や、老人医療担当課との面談を行い、開設の意向や場所、事業の目的・理念、運営方針などについて説明します。
政令指定都市以外の地域で開設する場合は、都道府県の担当者との面談も必要です。
事業計画の策定
指定申請に向けて具体的な事業計画を作成します。
設備整備計画、人員計画、資金計画、サービス計画など、運営に必要な要素について、単年度計画と3~5年の中長期経営計画を立てます。
この計画に基づいて、事務所の賃貸契約、設備・備品・物品の準備、人材確保のための採用活動、運営規定やマニュアルの作成など、具体的な準備を進めていきましょう。
資金の準備
事業計画の策定と同時に、資金の準備も進めます。
事務所や車両、設備、備品などを揃える開設資金と、人件費や光熱費など運転資金が必要です。
事業開始後、最初の収入は3カ月後となるため、最低でも3カ月、余裕を持たせるなら1年分の人件費(約1,000万円)を確保しておく必要があります。
資金調達の方法としては、自己資金のほか、日本政策金融公庫からの創業融資や、銀行・信用金庫からの融資などがあります。
指定申請手続き
設置基準を満たして準備ができたら、都道府県または市区町村に指定申請を行います。
訪問看護事業の指定は、介護保険法に基づく指定と、健康保険法に基づく指定がありますが、介護保険法の指定を受けることで、健康保険法による訪問看護事業者としてみなし指定を受けられます。
指定申請に必要なのは主に以下のようなものです(福岡県の場合)。
- 指定(許可)申請書
- 指定(許可)に係る記載事項
- 申請手数料
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 訪問看護ステーション管理者の免許証の写し及び経歴書
- 従業者の資格証・登録証の写し
- 平面図
- 運営規程
- 利用者様からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る誓約書(介護保険法第70条第2項関係)
- 当該申請に係る誓約書(福岡県暴力団排除条例関係)
- 災害時情報共有システムへの登録に係る調査票
- 業務管理体制に係る届出書
提出した書類に基づき、行政による審査、必要に応じて実地調査を受け、審査に通ると、1~2カ月ほどで通知書を受け取ることができます。
なお、指定を受けたあとも6年ごとに更新が必要です。
開業準備・開業
指定申請と並行して、開業に向けた最終準備を進めます。
賠償責任保険への加入、加算等の体制の届け出、業務管理体制の届け出などを行います。
また、地域の医療機関や居宅介護支援事業所との連携体制を構築することも重要です。
パンフレットの作成やWebサイトの開設など、利用者様獲得に向けた広報活動も行いましょう。
訪問看護の開設基準を確認し法令遵守で開設へ
訪問看護ステーションの開設には、人員基準、設備基準、運営基準という3つの開設基準を満たすことが求められます。
人員基準では常勤換算2.5人以上の看護職員と専従の管理者の配置が求められ、設備基準では専用の事務室や必要な設備や備品の確保が必須となります。
また運営基準には、サービス提供に関する基準と業務管理に関する基準が設けられており、それらをしっかり満たせるかも確認が必要です。
訪問看護ステーションを開設するには、法人設立、行政との事前協議、事業計画の策定、申請手続きなどを計画的に進める必要があります。
また、開設資金に加えて3カ月から1年分の運転資金を確保しておくことが望ましいです。
開設基準と手続きの流れを知り、地域に貢献できる質の高い訪問看護ステーションの開設を目指しましょう。